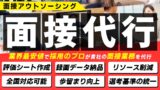「年功序列」と「成果主義」の違い
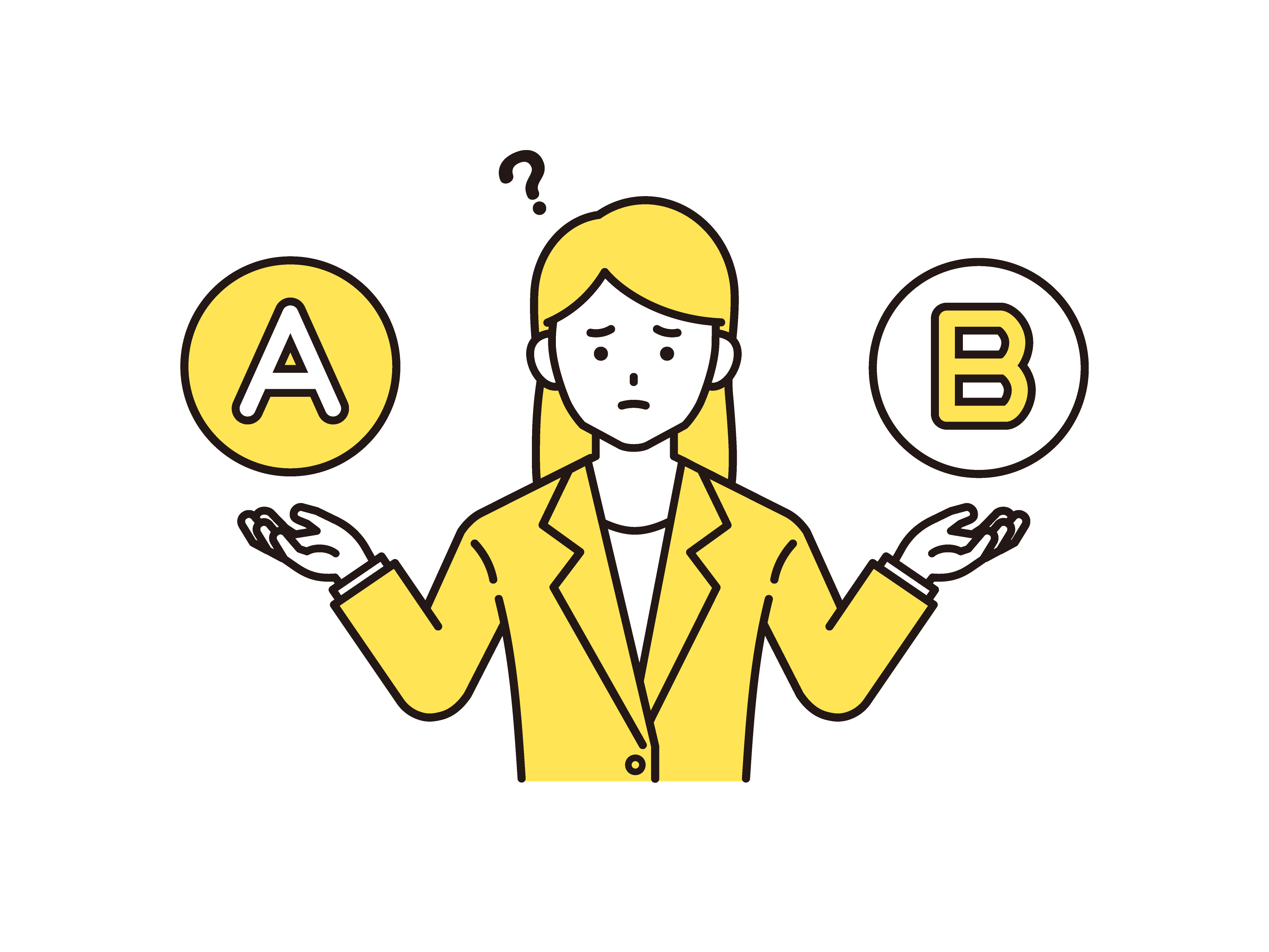
| 年功序列 | 成果主義 |
|---|---|
| 年齢・勤続年数を重視して評価 | 結果・成果物を重視して評価 |
| 定着率が高い傾向がある | 定着率が低い傾向がある |
| チャレンジ精神が低下しやすい | チャレンジ精神が向上しやすい |
| 帰属意識が高い | 帰属意識が低い |
| 年長者が多いと人件費が高騰する | 適切な場所に人件費を割ける |
| 評価が簡単で人事負担が少ない | 評価が複雑化し人事負担が大きい |
上記表のように、「年功序列」と「成果主義」の違いはその評価基準にあります。賃金の決定に勤続年数や年齢が重視される年功序列に対して、成果主義は結果重視とされています。それぞれの人事評価制度の特徴によって、社員の意識が大きく異なり、人件費や人事の負担だけでなく、経営自体に大きな影響があります。本記事では、「年功序列」と「成果主義」、それぞれのメリット・デメリットを含めた特徴を詳しく説明していきます。
年功序列とは?
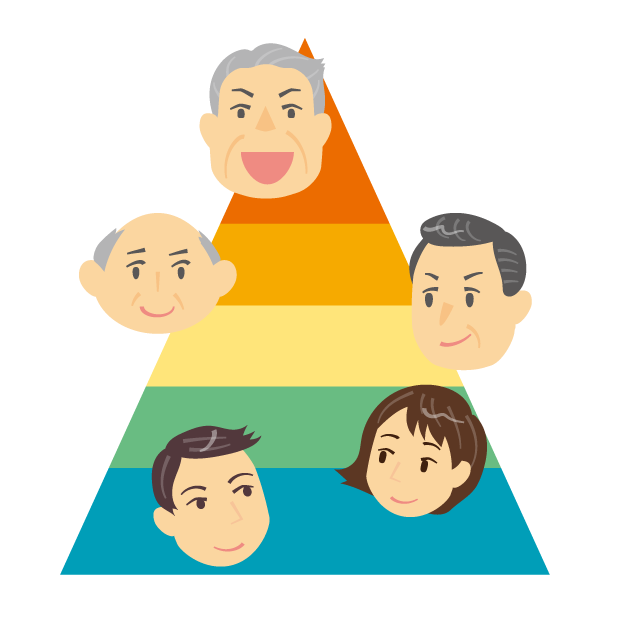
年功序列の意味
「年功序列」とは勤続年数の長さや年齢を重視して、給料が上がる賃金制度。勤続年数や年齢が高くなればなるほど、それに比例してスキルやノウハウ、経験といったものが蓄積され、組織内における職務上の重要度が高まるという考えです。高度経済成長期の日本経済が急成長していた時代背景と年功序列という仕組みの相性が非常に良く、戦後の日本経済発展を支えてきました。
年功序列のメリット
- 既存社員の定着率向上
- 若手社員の教育体制の万全化
- 管理の簡略化によるコスト削減
1. 既存社員の定着率向上
最大のメリットは、勤務年数により賃金は上昇し、昇給の可能性も高くなることから、長期勤務を前提として働く人が増えることです。また、長期間一緒に働いていると社員同士の理解・関係構築が深まりチームワーク力が向上するというメリットもあります。
2. 若手社員の教育体制の万全化
年功序列制度が定着している組織には、社歴の長い社員が多く在籍しているため、新入社員・若手の育成ができる人材が揃っているので、組織内の育成をスムーズに行えるポイントも大きなメリットの一つです。
3. 管理簡略化によるコスト削減
年功序列では「勤続年数の長さ」や「年齢」によって人事評価を進めるため、成果や青果物を比較する手間と時間がかからず、人事評価基準が明確なことから、人事評価にかかる人的・時間的コスト削減ができる点もメリットです。
年功序列のデメリット
- 社員のモチベーション低下
- 年長の従業員増加による人件費の高騰
- 有能な社員の離職率が高まる
1. 社員のモチベーション低下
年功序列では、成果とは無関係に人事評価が行われるため、「加点方式」より「減点方式」での評価が多くなります。そうなると「頑張ってもお給料は一緒だからやる気が出ない・・・」といった社員が増え、新しいことにチャレンジする意欲が湧かず、モチベーションが上がらない組織になります。
2. 年長の従業員増加による人件費の高騰
新卒・若手社員の採用数を増やし続け、利益をコンスタントに伸ばすことができれば、年功序列は上手くいきます。ですが、若手社員が増えず、年長者が増え続けると人件費が占める割合が高くなるため、経営方針上、早期退職を促したり、リストラを検討しなければなくなります。
3. 有能な社員の離職率が高まる
年功序列の特徴として一般的には、離職率の低さが挙げられますが、有能な人材は、能力を発揮して一定以上の成果を上げても正当な評価を得ることができないため、能力を正当に評価してくれる会社に転職してしまうことから、将来有望な社員ほど離職してしまう傾向にあります。こうなると、「組織に残るのは質の悪い社員ばかり」ということにもなりかねません。
成果主義とは?
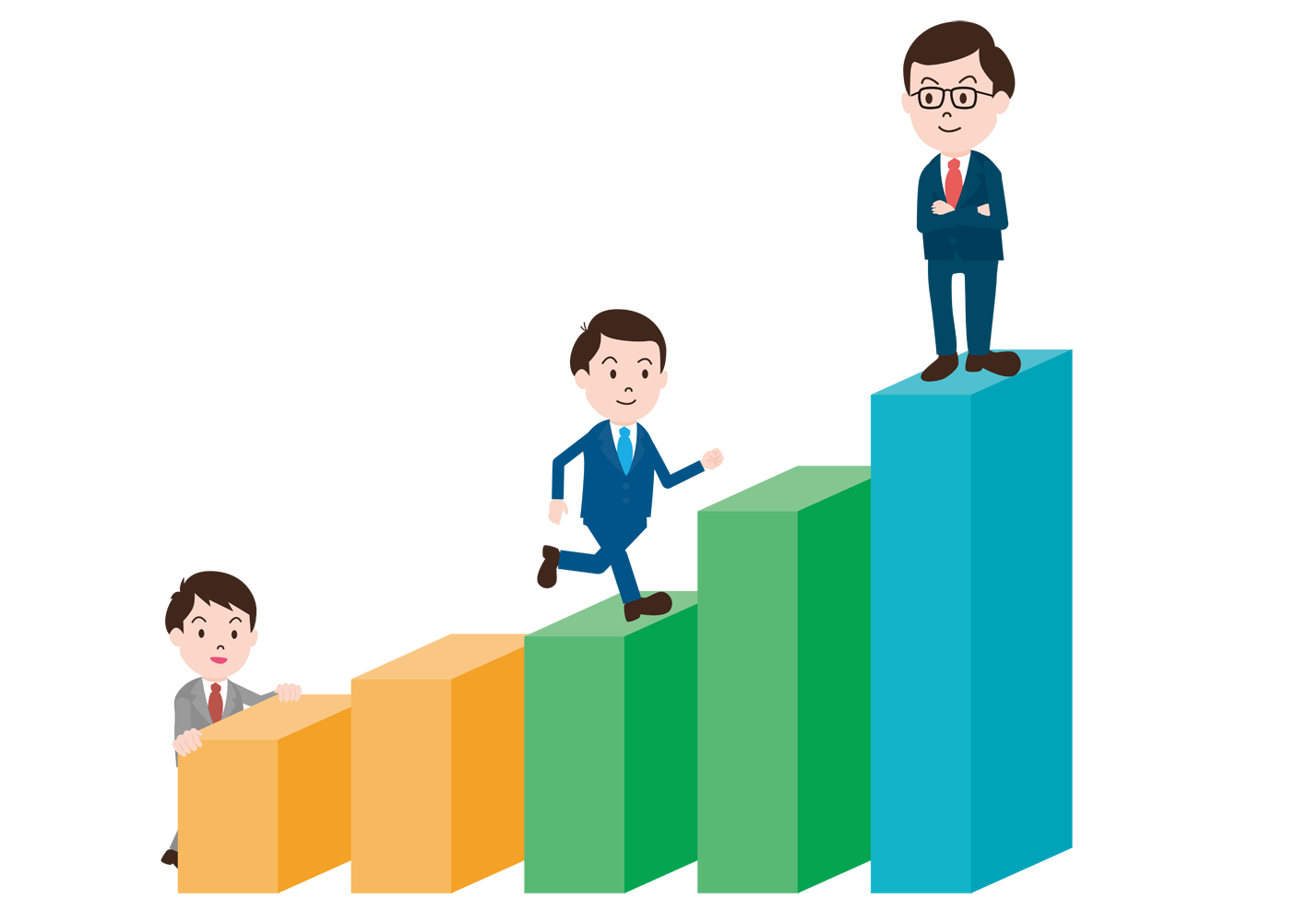
成果主義の意味
「成果主義」とは仕事の成果や成績などの「実力」に重点を置く賃金制度です。年功序列の対義語として使われることが多いのがこの成果主義です。勤務時間・年齢・社歴・経験などではなく、最終的に出した成果で評価が決まりますが、その一方で、ベテラン社員であっても成果を出せない社員は評価が下がることになるという側面を持っています。欧米諸国ではこの「成果主義」が一般的となっており、成果が出せれば高待遇、成果が出せなければ給料が下がるかクビとなります。バブル崩壊後は年功序列を続けるのが厳しくなったため、日本でも「成果主義」を導入する企業が増えています。
成果主義のメリット
- 正当な評価によるモチベーションUP
- 余計な人件費・経費を削減
- 大幅な生産性の向上
1. 正当な評価によるモチベーションUP
「成果主義」の最も大きなメリットとしては、成果に応じて評価が決定しているため、実力に見合った給料がもらえるという点です。成果が出せた分が給料に直結するので、自然と社員のモチベーションが上がりやすい傾向があります。また、「年功序列」とは違い、社員の高齢化により人件費が増加していくということもありません。
2. 余計な人件費・経費を削減
「年功序列」では、組織への貢献度の低い社員であっても、勤続年数や年齢に比例して相応の賃金を支払う必要がありますが、「成果主義」の場合は、貢献度が低い社員への給料を減らすことができるため、会社側としては余計な人件費の発生を防げるというメリットがあります。
3. 大幅な生産性の向上
「成果主義」は結果が全てなので、成果を出すためには実力をつける必要があり、スキルアップのために自然と社員がやる気を出して頑張るようになります。社員1人1人が効率化を意識した働き方を目指すことで、組織全体の生産性が大幅に向上させることができます。
成果主義のデメリット
- 社員のモチベーション低下
- チーム力の減少・個人プレーの増加
- 離職率の上昇
1. 評価基準の不透明性による社員の不満
「成果主義」では、年齢や社歴だけで評価できる「年功序列」に比べると適正な評価が難しい傾向があります。例えば営業職のように、数字として成果が表せる職種であれば管理はさほど難しくありませんが、成果を数値化できない職種では、どうしても評価者の主観に左右されてしまい、不公平感が生じることがあり、社員の不満へと繋がることがあります。
2. チーム力の減少・個人プレーの増加
「成果主義」では、社員個人がどのような成果を上げたかという点に着目して評価されるため、社員同士が悪い意味でのライバル意識を持ち、チームワークが崩れて人間関係が難しくなることがあります。また、「チームとしての成果」が軽視されることで、場合によっては企業全体の成果が下がることにもなることも・・・。
3. 離職率の上昇
成果が出せず報酬が上がらない社員としては、モチベーションが低下するため離職率が増加する傾向があります。一見すると、優秀な社員のみが残ることで組織としては良い結果に思いがちですが、人が減ることで既存社員一人一人の業務負担が増え、キャパオーバーを引き起こす社員が出てきます。求人にかかるコストも増加し、新人育成のためにさらに人員が必要になってきます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。コロナ禍を経て組織の体制が変わりつつある現在では、「年功序列制度」を取り入れる企業数も「成果主義制度」を取り入れる企業数も、どちらも増えていくと予想されています。「年功序列制度」も「成果主義制度」も、それぞれにメリットとデメリットがありますので、どちらがより自分に合っている制度なのかを考えてから、企業選択・業界選択をしていくと、思わぬトラブルによる早期退職という可能性を下げることができると思います。